第二種電気工事士 学科試験の流れと必ず押さえたい勉強ポイント
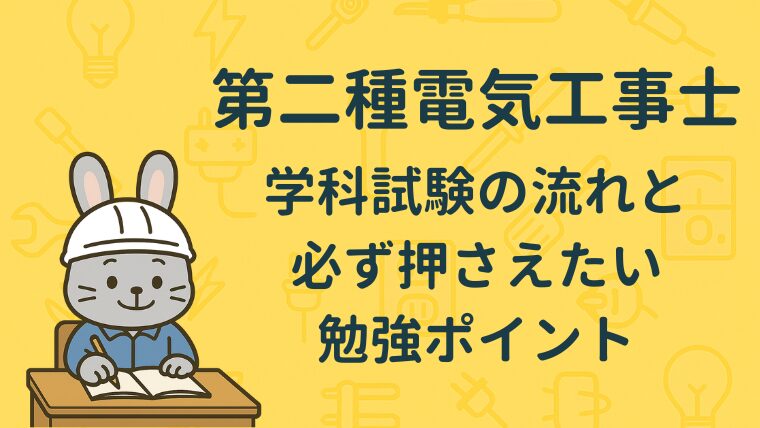
第二種電気工事士の学科試験は、電気工事の基礎知識を問う重要なステップです
この記事では、学科試験の全体像と合格に近づくための効果的な勉強ポイントをわかりやすく解説していきます!
目次
学科試験の基本情報
第二種電気工事士の学科試験は、マークシート方式で出題されます
問題数は50問、制限時間は120分です
試験は年に2回実施され、上期は5月に筆記試験、7月に技能試験、
下期は10月に筆記試験、12月に技能試験が行われます
出題分野は以下の4つに分かれています
- 電気に関する基礎理論
- 配線設計・施工方法
- 器具や材料に関する知識
- 電気関連法規
合格基準は60%以上、つまり30問以上の正答が必要です
試験の難易度と出題傾向
学科試験の合格率は、例年およそ50〜65%の間を推移しています
難易度は高すぎるわけではありませんが、油断せずに対策することが重要です
試験問題の多くは過去問からの出題がベースになっており、同じような問題パターンが繰り返し登場します
そのため、過去問学習が非常に効果的です
特に出題頻度が高いテーマとしては、オームの法則、単相三線式回路、接地工事、電線の太さ選定などが挙げられます
また、最近ではCBT方式(パソコンで解答する試験形式)が採用されるケースが増えているため、パソコン操作に慣れておくことも大切です
効果的な勉強ポイント
過去問を徹底的に活用する
過去問は最大の教材です 少なくとも直近5年分を3周以上解くことを目標にしましょう
間違えた問題を重点的に復習することが合格への近道です
苦手分野を早めに洗い出す
一通り学習を進めたら、どの分野が苦手かを明確にしましょう
電気理論が苦手なら重点的に演習を増やす、法令が苦手なら頻出条文だけに絞って覚えるなど、苦手克服に時間をかけます
図やイメージで覚える
特に配線図や回路図は、図を描きながら理解することが重要です
目で見て覚えることで、知識が確実に定着します 実技試験にもつながる部分なので、図解学習を意識しましょう
CBT方式に慣れておく
CBT方式では、パソコン画面に表示された問題をマウスやキーボードで操作して解答します
紙の試験とは感覚が違うため、事前に模擬試験サイトやアプリを活用して慣れておくと安心です
試験当日に戸惑わないためにも、CBT練習は必ず取り入れましょう
電気技術者試験センター公式サイトでは、学科試験(CBT方式)体験版を公開しているようです
実際の試験画面に近い環境で練習できるので、ぜひ事前に体験しておきましょう
→ 学科試験(CBT方式)体験版はこちら(電気技術者試験センター公式サイト)
よくある失敗例と対策
時間配分をミスする
学科試験は50問を120分で解答しますが、問題によっては時間がかかるものもあります
難しい問題にこだわりすぎず、わかる問題からテンポよく進めることが大切です
見直しの時間を確保するためにも、1問あたり2分以内を目安に解答しましょう
暗記だけに頼ってしまう
知識を丸暗記するだけでは、少し出題パターンが変わったときに対応できません
なぜその答えになるのか、理由まで理解する意識を持ちましょう
直前だけ詰め込む
短期間の詰め込みでは忘れやすく、本番で思い出せないリスクが高まります
少なくとも試験日の2か月前から、毎日30分以上の学習を継続することが理想です
まとめ
第二種電気工事士の学科試験は、ポイントを押さえて地道に積み重ねれば、誰でも合格を目指せる試験です
過去問を中心に苦手分野をつぶし、試験形式に慣れておくことが合格への近道です
焦らず、着実にステップを踏んでいきましょう
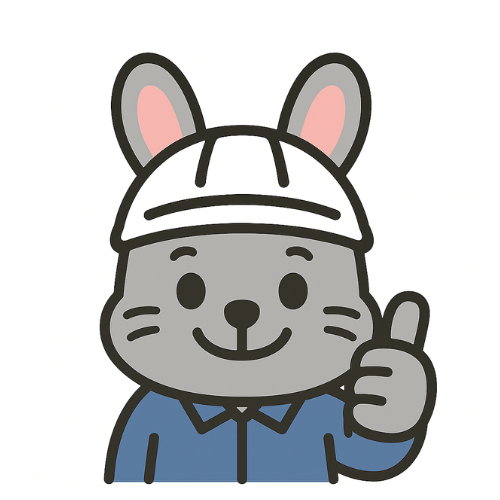
今日できる小さな一歩が、未来の自分を大きく変える力になります
焦らず着実に、確実に前へ進みましょう
電工ラビットは、いつでもあなたを応援しています!





