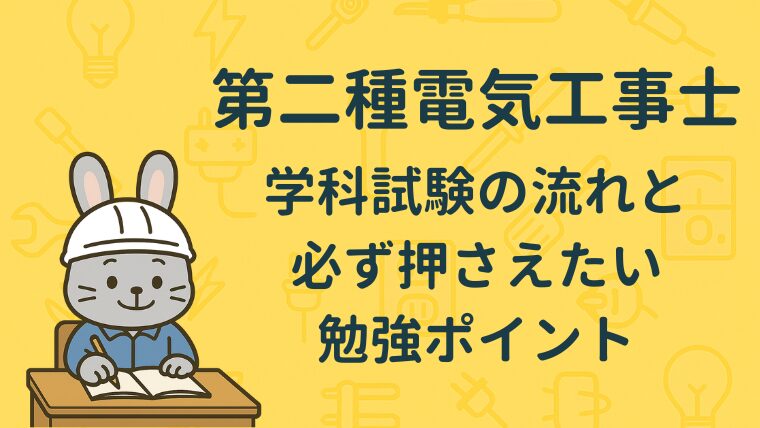【完全理解】第二種電気工事士のための電気抵抗|電気の通りにくさを感覚でつかもう

電気抵抗という言葉、聞いたことはあってもその正体は意外とあいまいなままになっていませんか?
「抵抗が大きいと電気が流れにくい」と聞いても、どれくらい影響があるのか、実感しにくいのが本音かもしれません
この記事では、図解なしでも感覚的につかめるように、電気抵抗の仕組みや計算方法、試験によく出る合成抵抗の考え方を丁寧に解説します
試験対策としてだけでなく、実務の現場でも活きる知識として、しっかりマスターしていきましょう!
目次
電気抵抗とは?電気の通りにくさを表す値
電気抵抗とは、電気の流れを妨げる“通りにくさ”を数値で表したものです
電線の中で、電気がスムーズに流れるのか、それとも流れにくいのかを判断するための指標といえます
抵抗が大きいと、電流が流れにくくなり、エネルギーが熱として失われることもあります
配線の長さや材料、太さなどで抵抗値は変わるため、正しく理解することが重要です
たとえば、長い延長コードを使ったときに、電圧が下がって機器が正常に動かない場合がありますが、それは抵抗による“電圧降下”が原因です
なぜ電気抵抗を理解する必要があるのか
電気抵抗の知識は、試験対策だけでなく、実務でも不可欠です
- 電圧をかけても電流が流れない原因がわかる
- 適切な電線サイズや長さを選べる
- 抵抗の合成方法がわかると、配線設計ができる
第二種電気工事士試験でも、オームの法則を使った抵抗計算や、複数抵抗の合成問題が頻出します
また、現場では「なぜこの電線では足りないのか」、「この機器にはどれだけの抵抗が許容されるのか」といった判断の材料にもなるため、理解しておく価値は非常に高いです
電気抵抗のイメージを言葉でつかむ
抵抗の大きさを「通り道の幅」でイメージすると分かりやすくなります
- 太い道(抵抗が小さい)→ 電気がスイスイ流れる
- 狭い道(抵抗が大きい)→ 電気が詰まりやすい
抵抗が小さい=スムーズに流れる、 抵抗が大きい=流れが鈍る、という感覚でとらえましょう
また、よく見かける「白熱電球」も実は電気抵抗を利用した機器の代表例です
フィラメントの部分が高抵抗であることで、電流が流れると発熱し、その熱で光を発しています
つまり、抵抗=悪いものではなく、正しく使いこなすことで電気を有効に利用する仕組みでもあります
電気抵抗の基礎知識まとめ(用語・単位・記号)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位 | オーム(Ω) |
| 記号 | R |
| 測定機器 | テスター(抵抗モード) |
| 材料との関係 | 導体(銅・銀):小さい / 絶縁体(ゴム・ガラス):大きい |
抵抗はオームの法則でも使われる
オームの法則では、電圧(V)と電流(I)から抵抗(R)を求めることができます
【公式】R = V ÷ I
この公式を覚えておくと、いろんな計算に応用できます
例: 電圧60V、電流2Aの場合 → R = 60 ÷ 2 = 30Ω
抵抗の計算と合成抵抗(公式と例題)
抵抗が並列の2個だけのときは「かけて足して割る」
並列につながった2つの抵抗は、次の方法で合成抵抗を出せます
参考書などには和分の積と書かれていますが、今回は「かけて足して割る」でいきましょう
「2つをかけて、その合計で割る」 → かけて、足して、割る!
例: 20Ωと30Ω → 20×30=600、20+30=50、600÷50= 4Ω
※ これは2つだけのとき限定です。3個以上では使えませんので気をつけてください
直列と並列の合成方法
- 直列:そのまま足す → R合成 = R1 + R2 + R3
- 並列:逆数を足して、さらに逆数にする → 1/R = 1/R1 + 1/R2 + …
- 例題① 10Ωを3つ直列に接続したとき、合成抵抗は何Ωですか?
-
R = 10 + 10 + 10 = 30Ω
- 例題② 20Ωと30Ωを1つずつ並列に接続したとき、合成抵抗は何Ωですか?
-
1/R = 1/20 + 1/30 = 5/60 → R = 12Ω
または、20 × 30 = 600、20 + 30 = 50、600 ÷ 50 =12Ω
「かけて足して割る」
- 例題③ 40Ωと60Ωを並列に接続して、それに30Ωを直列に接続したとき、合成抵抗は何Ωですか?
-
並列部分:40 × 60 = 2400、40 + 60 = 100、2400 ÷ 100 = 24Ω
直列部分:24(上の並列部分) + 30 = 54Ω
- 例題④ 10Ωと15Ωと30Ωの3つを並列に接続したとき、合成抵抗は何Ωですか?
-
1/R = 1/10 + 1/15 + 1/30 = 6/30 → R = 5Ω
よくある間違いと補足解説
- 直列と並列の違いを混同する → 並列は“逆数の和”、直列は“そのまま足す”
- 導体と絶縁体の性質を取り違える → 銅や銀は抵抗が小さく、ゴムや木は抵抗が大きい
- 電線の長さと抵抗の関係を見落とす → 抵抗は「長さに比例・太さに反比例」です
- オームの法則で単位を忘れる → V(ボルト)÷ I(アンペア)= R(オーム)を意識しましょう
一問一答で抵抗の理解チェック!
- 抵抗の単位は何ですか?
-
オーム(Ω)
- 抵抗の記号は何ですか?
-
R(アール)
- V=12V、I=2Aのときの抵抗は何Ωですか?
-
12V ÷ 2A = 6Ω
- 電線が長く細いほど抵抗はどうなりますか?
大きくなる、小さくなる -
大きくなる
- 10Ωと10Ωを並列にすると合成抵抗は何Ωになりますか?
-
5Ω
10 × 10 = 100、10 + 10 =20、100 ÷ 20 = 5
まとめ:抵抗を制する者が配線を制す!
- 抵抗は電気の通りにくさを数値で表したもの
- 小さい抵抗=流れやすい、大きい抵抗=流れにくい
- 合成抵抗の計算方法は、直列と並列で異なる
- 白熱電球や電熱器なども、抵抗を利用した製品
- 抵抗は電気の基本であり、試験でも実務でも重要なテーマ!
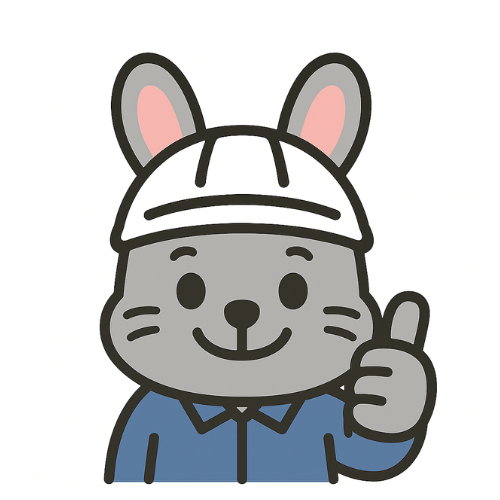
抵抗の仕組み、つかめてきましたか?
最初はややこしく感じるけど、ポイントをつかめばもう怖くないです!
直列? 並列? 計算ミスに注意しながら、一緒にもっとレベルアップしていきましょう!
実務でも抵抗は超重要です!
いっしょに最後までがんばりましょう!