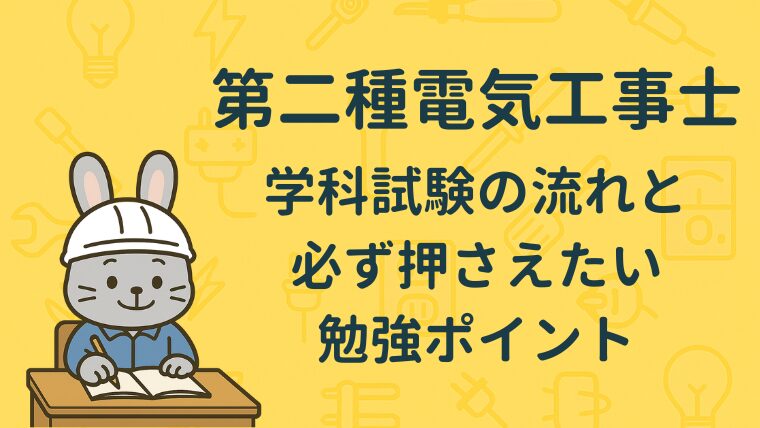【完全理解】第二種電気工事士のための電圧|電気を押す力を感覚でつかもう

第二種電気工事士の試験に向けて「電圧ってなんだかピンとこない…」と思ったことはありませんか?
電圧とは電気を流すための“押す力”ですが、言葉だけだとイメージしにくいのも確かです
この記事では、身近なたとえを使って電圧をやさしく解説します
試験対策としてだけでなく、実際の現場でも役立つ考え方をしっかり身につけましょう!
目次
電圧とは?電気を動かす“力”を知ろう
電圧とは、電気を動かすために必要な「力」のことです
具体的には、電流を流そうとする力であり、電気の流れを生み出す源なのです
この力がなければ、いくら電線や機器をつないでも、電気はまったく流れません!
電圧を理解するとなぜ役立つのか
第二種電気工事士の試験では、電圧の知識は計算問題・配線問題の両方に関わってきます
電圧を正しく理解することで、以下のような力が身につきます
- 電気がなぜ流れるのかを説明できる
- 安全に機器を使うための注意点がわかる
- 電流や抵抗との関係を使って計算できる
また、現場では電圧の違いによる誤接続や、電圧降下によるトラブルを防ぐためにも 電圧の理解は欠かせないのです
電圧のたとえ話でつかむ感覚
電圧は「押す力」ですが、もっとわかりやすくするなら “坂道”や“水道”のたとえが使えるかなと思います
- 坂道でたとえると、坂の上が高電圧、坂の下が低電圧です
高いところから低いところへ物が転がるように、電気も高電位から低電位へ流れていきます - 水道でたとえると、水を押し出す水圧が電圧です
水圧が高ければ水は勢いよく出ていき、電圧が高ければ電流もよく流れるということですね
このように、電圧は「高さ」や「圧力」としてイメージすると覚えやすくなりますよ
電圧の基礎知識まとめ(用語・単位・測定)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位 | ボルト(V) |
| 記号 | V |
| 測定方法 | テスター、電圧計で測定 |
| 流れる方向 | +極(高電位)から−極(低電位)へ |
電圧の高さは、乾電池1個なら1.5V、家庭のコンセントは100V、 工場では200V以上の電源を使う場合もあります
電圧がなければ電気は流れない
電圧があるからこそ、電流が生まれます
逆に、電圧が0Vであれば、どれだけ電線がつながっていても電気は流れません!
つまり、電圧は「流れの原動力」です
電気を動かすエネルギーの“差”として理解することが大切です
試験で必須のオームの法則(公式と例題)
電圧と電流、抵抗の関係を示す最も重要な式が「オームの法則」です
【公式】V = I × R
- V:電圧(V:ボルト)
- I:電流(A:アンペア)
- R:抵抗(Ω:オーム)
この公式は、以下のように使い分けます
- 電流と抵抗から電圧を求める:V = I × R
- 電圧と抵抗から電流を求める:I = V ÷ R
- 電圧と電流から抵抗を求める:R = V ÷ I
練習問題
- 例題①: 抵抗(R)が10Ω、電流(I)が2Aのときの電圧(V)は何Vですか?
-
電圧(V) = 10Ω × 2A = 20V
- 例題②: 電圧(V)が12V、抵抗(R)が4Ωのときの電流(I)は何Aですか?
-
電流(I) = 12V ÷ 4Ω = 3A
- 例題③: 電圧(V)が60V、電流(I)が2Aのときの抵抗(R)は何Ωですか?
-
抵抗(R) = 60(V) ÷ 2(A) = 30Ω
よくある間違いと補足解説
- 違う電圧の機器を接続する事故 → 12Vの機器に100Vを接続すると一瞬で壊れてしまいます
必ず接続する機器の定格を確認しましょう! - 電池の直列・並列の勘違い → 直列は電圧が足し算なので電池が1つのときより明るくなります
並列は電圧がそのままだけど、電池が1つのときより長く使えます - 電圧の向きと流れの勘違い → 電気は+から−に流れます(理論上)
一問一答で理解をチェック!
- 電圧の単位は?
-
ボルト(V)
- 電圧が0Vのとき、電流は?
-
流れない(0A)
- V=12V、I=2A、Rは何Ω?
-
12(V)÷2(A)=6Ω
- 電池1.5Vを2本直列につなぐと何V?
-
3V
まとめ:電圧の理解は電気の第一歩
- 電圧は「電気を押す力」
- 高いところ(高電位)から低いところ(低電位)に向かって電気は流れます
- オームの法則で電圧・電流・抵抗はセットで考えましょう
- 間違った接続をすると機器を壊す危険があります
電圧を正しく理解すれば、電流や電力の知識もスムーズに身についていきます
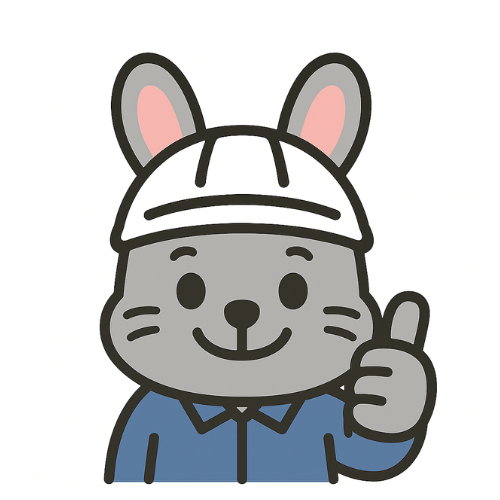
電圧のこと、いろいろ学べましたね
電気のスタートはここからです!
電圧を押さえた今なら、次の「電流」や「電力」もきっとスッと入ってくると思います
一緒にもっと電気の世界を楽しみましょう!