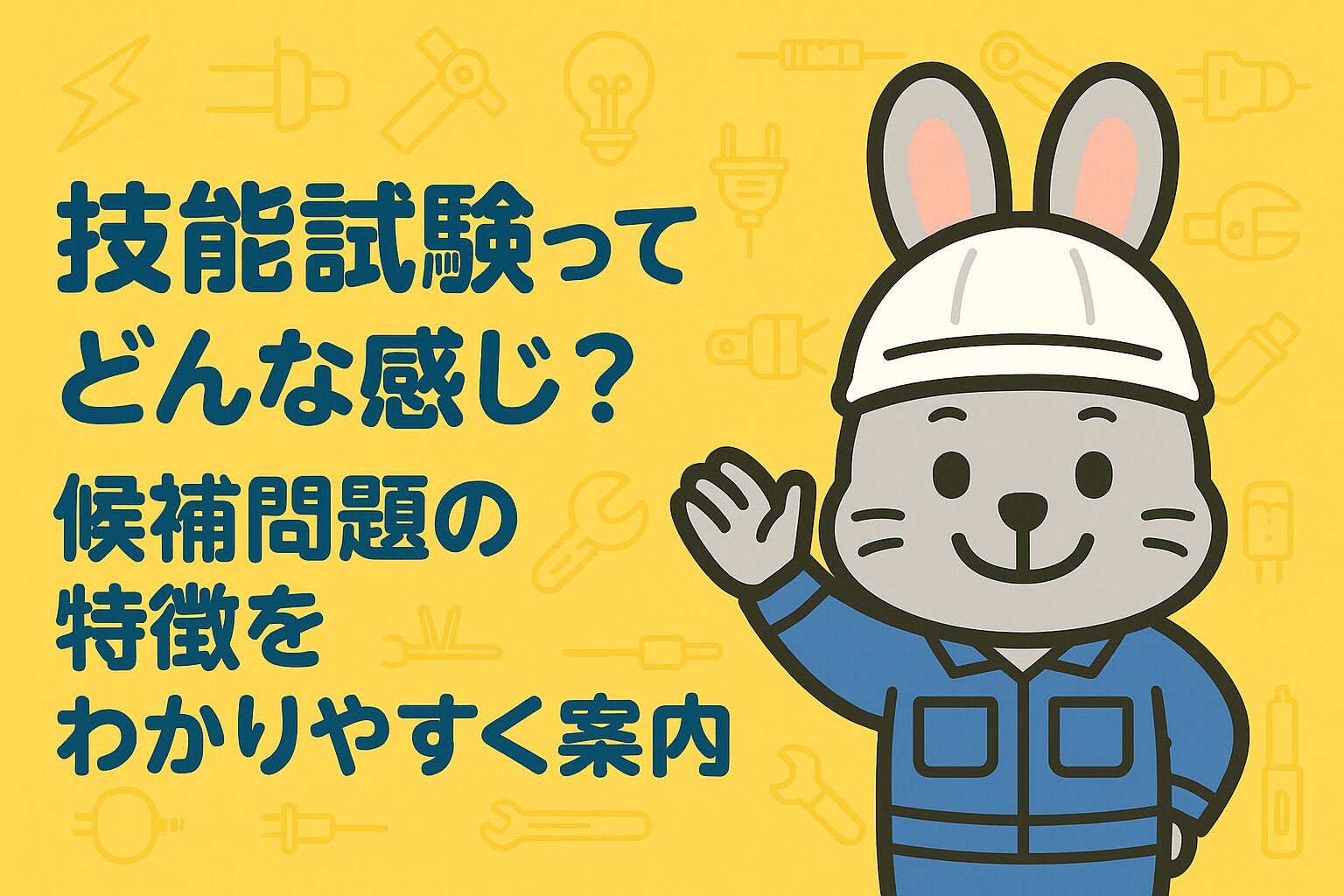第二種電気工事士|ありがちな失敗パターンと回避のコツ【技能対策】

目次
技能試験のミスは“準備と確認”で防げる
第二種電気工事士の技能試験では、一発勝負の緊張感の中で「ケーブルの長さが足りなかった」「結線ミスに気づかなかった」など、惜しいミスで不合格になる人が少なくありません
でも安心してください
これから紹介する失敗パターンとその回避法を事前に知っておくだけで、合格に一歩近づけます
技能試験は“段取り勝負”です 本番で焦らず手を動かせるよう、この記事で一緒に準備していきましょう
作業別に解説!ありがちなミスとその対策
ケーブルの長さが足りない(配線不足)
よくある状況
VVFケーブルを必要最小限の長さで切ってしまい、器具に届かない
対策
カット前に実際に器具にあてて長さを確認して、10cmほど余裕をもって切り出すのが安全圏
圧着端子のミス(不完全な圧着)
よくある状況
リングスリーブに芯線がしっかり入っていない、または圧着マークが見えにくい
対策
2度見で確認(圧着後に必ず目視)
芯線をそろえ、スリーブに奥まで差し込むことを習慣に
結線ミス(スイッチやコンセントの誤接続)
よくある状況
複線図通りに接続できず、LとNが逆、スイッチが効かないなどのトラブル
対策
練習時から複線図を何度も書いて頭に入れる
「指差し確認」で配線の向きをチェック
被覆の剥きすぎ・剥き足りない
よくある状況
芯線が見えすぎてショートの原因になったり、逆に剥き足りずに接続が甘くなる
対策
スケールで剥き長さを毎回測るクセづけ
工具のガイドを活用して、適切な長さを覚える
試験当日に差がつく!チェックリスト活用法
作業前:試験課題と材料の確認
- 支給された材料がそろっているか確認
- 器具の種類や向きに注意(特にスイッチ・コンセント)
- 材料を見た瞬間にどの候補問題かを推測できるようにしておくと、複線図が自然と頭に浮かぶ
- この“瞬間判断力”は、練習の積み重ねで誰でも身につけられる
作業中:時間配分にメリハリを
- 全体の試験時間は40分間です
- 特に慣れないうちは、時間内に終わらせるだけでも大変なケースがほとんどです
- 開始から15分ほどは配線の仮置きと大まかな接続に集中
- その後は接続・仕上げ・見直しの時間配分を意識して進めましょう
- 「残り10分で必ず全体を見直す」というのは理想ですが、実際には難しいこともあります
- 最低でも残り3〜5分で手を止めて全体を確認する習慣をつけておくと安心です
- 器具のネジ緩み・結線ミス・被覆長さなどは最後に確認するだけで失点を防げるポイントです
作業後:完成チェック3ステップ
- 器具のネジ緩みなし
- 結線に間違いなし
- 全体の見た目がきれい(配線が暴れていない)
練習で身につけよう!ミスを減らす習慣づくり
複線図は“見ないで描ける”ようにする
出題パターンは限られています 何度も手を動かして、頭で考えずに描けるレベルを目指しましょう
練習記録をつける
- 毎回の練習でミスした箇所を記録
- 次回同じことをしないようにチェックリスト化 → 「ミスを見える化」すると、自然と精度が上がります
まとめ|失敗しない人は“確認と冷静さ”を持っている
技能試験でミスが起きるのは、ほとんどが準備不足か確認不足です
冷静に、順番を守って作業すれば、焦らず着実に仕上げられます
そして何より大事なのは「ミスしても、次に活かすこと」
今のうちにたくさん失敗して、その原因と対策を自分の言葉で説明できるようになっておきましょう
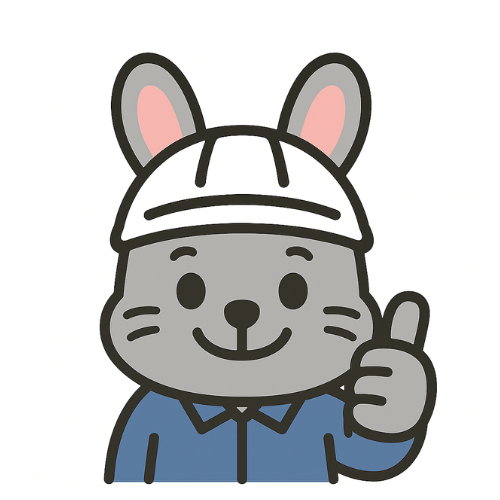
ミスは誰でもするけど、対策ができる人は強いです
試験当日は落ち着いて、ひとつひとつ丁寧にやれば大丈夫!
焦らず、自分のペースで合格をつかみましょう